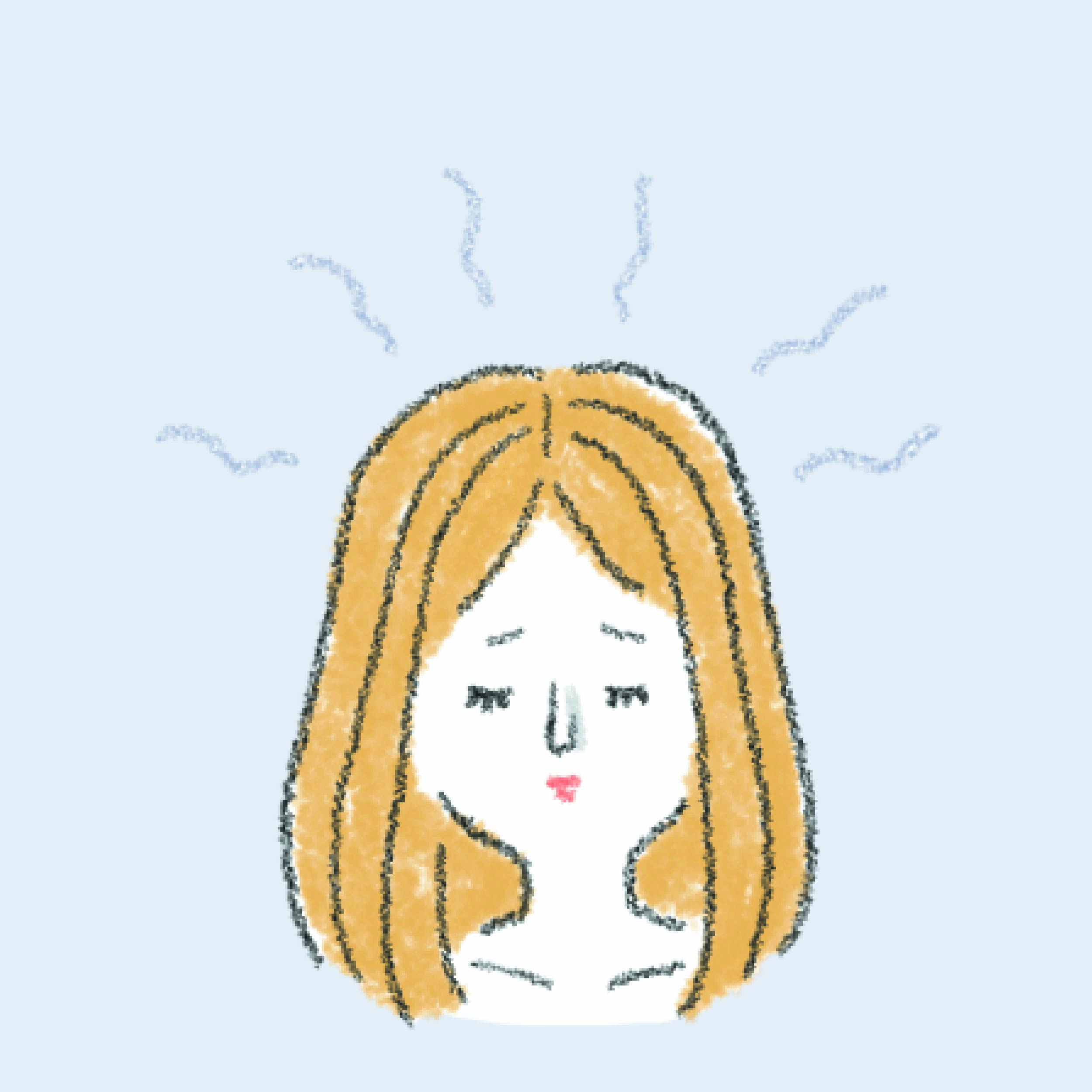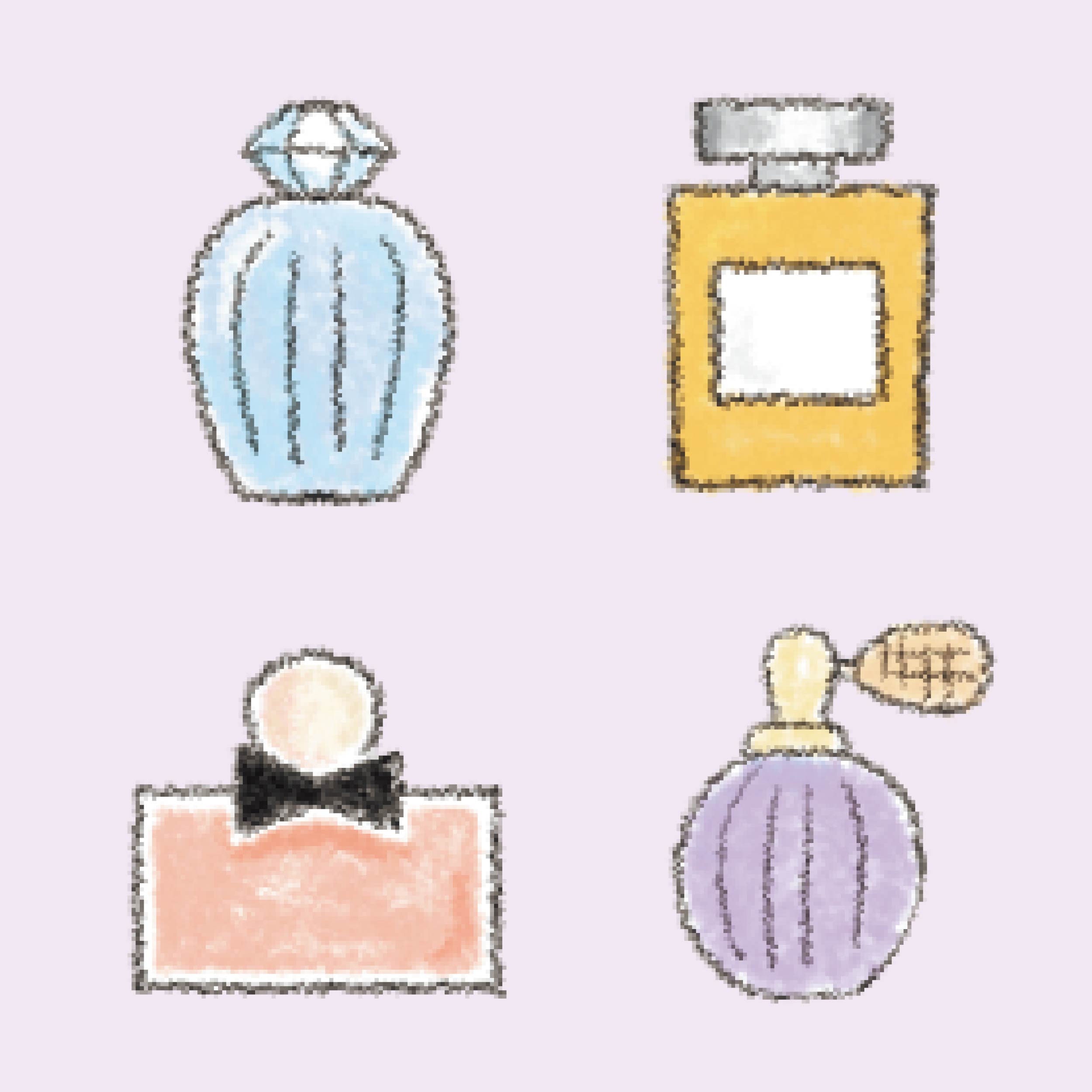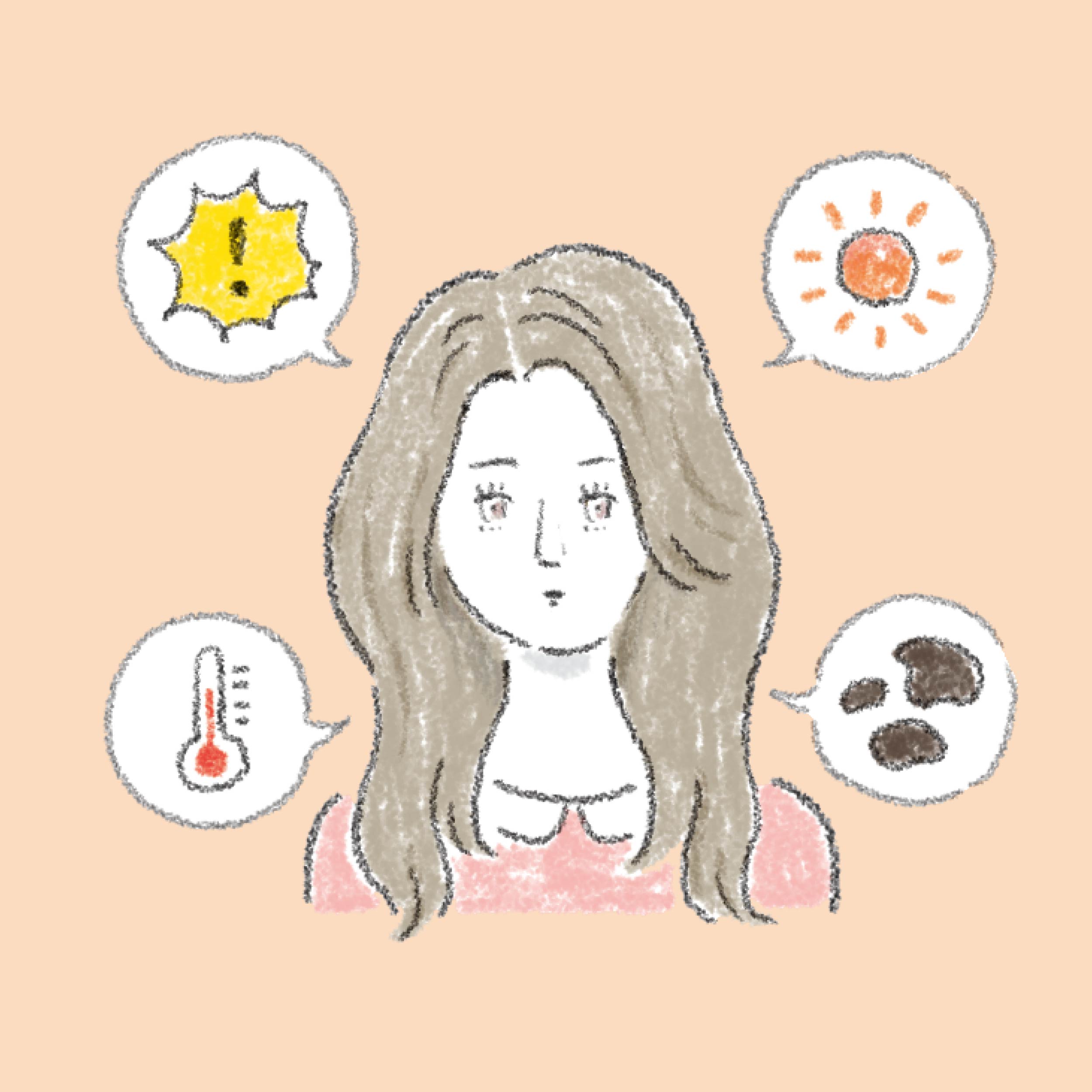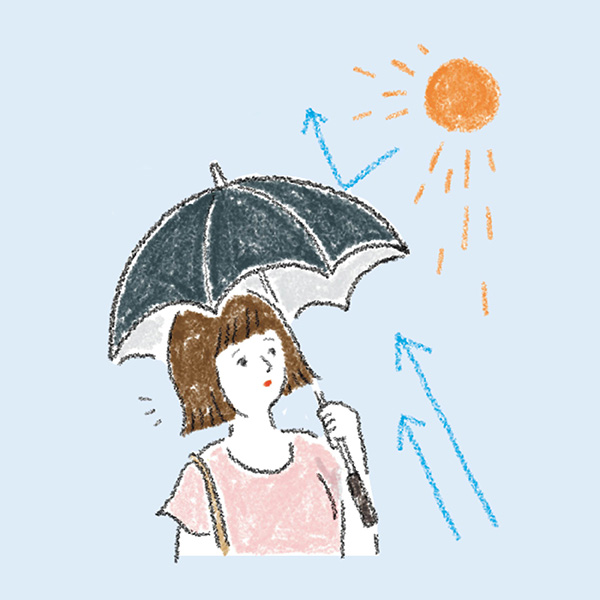腸内環境と肌の、深い関係
腸内環境は、肌にどう影響するの?
まずは、腸内環境のお話から。そもそも腸内では、3つの種類の常在菌が働いています。腸内の活動を活発にする善玉菌、腸内の腐敗を進めてしまう悪玉菌、善玉菌と悪玉菌の様子を見て活動する日和見菌。それぞれのベストなバランスは《善玉菌20%、悪玉菌10%、日和見菌70%》といわれていて、比率が崩れることで腸内環境も崩れてしまうんです。
腸内環境の悪化により肌荒れを起こしてしまう主な原因は、悪玉菌が増えてしまうこと。悪玉菌が発生させる有害物質が腸に吸収され、血液を介して全身をめぐり、汗や皮脂と一緒にカラダの外へ排出されます。そのとき、肌への刺激になったり、ターンオーバーが乱れたりして肌トラブルにつながってしまうんです。
また、腸内の悪玉菌が増えると肌の弾力を保つ機能を老化させる成分が発生することも。放っておくと、シワやたるみ、くすみの原因になってしまいます。
あなたの腸内環境、大丈夫?腸内環境チェックリスト
2つ以上チェックがついたら要注意!
腸内環境が乱れているかもしれません。
食生活を見直してみて!
すはだ美人になるためのHINT
HINT 01腸内環境を整えるために、食物繊維とオリゴ糖を摂るのが正解!
腸のぜんどう運動を促進させる食物繊維と、善玉菌のエサになるオリゴ糖は積極的に摂りましょう。オリゴ糖として販売されているものはもちろん、バナナやきな粉などにも含まれています。hugkumi+が販売しているはぐくみオリゴもおすすめです♪
HINT 02腸内の菌たちは温かいところが大好き!口にするものは温かいものが◎
人のカラダの深部の体温は37度前後。菌がいちばん居心地が良いのはこれくらいの温度なんです。
カラダの深部の温度が低くなってしまうと、菌の活動も抑えられてしまいます。カラダは冷やさないよう気をつけましょう。
HINT 03運動はやっぱりカラダに良い!毎日の中に取り入れられるものを。
適度な運動は、腸の働きを活性化させます。とはいえすぐに運動をするのは難しいので、まずは生活の中に取り入れられる、短い時間でできるものからはじめてみて。理想的な運動量は、1日に9,000歩前後のウォーキング(1時間半程度)と言われています。
HINT 04食事はゆっくりが基本。しっかり噛んで食べることで消化がスムーズに。
消化がスムーズであれば、腸内環境は整いやすいもの。日本人は比較的胃酸の分泌量が少ないとされているため、よく噛んで食べることで胃での消化を助けることができます。ひと口につき30回以上噛むことが理想。急いで食べずに、ゆっくり食事を楽しんでみて。
ところで…腸内フローラってなに?
腸内フローラとは、善玉菌や悪玉菌などの腸内常在菌群のこと。腸内にお花畑(フローラ)のように種類ごとに群生していることから、そのように呼ばれるようになりました。腸内に生息している菌は、1000種1000兆個以上ともいわれ、最近の研究では太りやすい・痩せやすい体質も、腸内の細菌と関係しているという結果も出ているんだとか。
すはだ美人は腸がキレイ!すはだ美人の腸活TODOリスト
カラダの中からキレイになるためには、なにをしたらいい?食生活を変える?運動?
腸内環境を整えて、すはだ美人になるためのTODOリストをご紹介します♪
【食生活を考える】健康のためには、自分に合った発酵食品を見つけて、毎日発酵食品を摂ることが大切です。
甘酒
飲む点滴とも言われる栄養満点の食品。
おやつ感覚で取り入れられるかも。
味噌
調味料だから取り入れやすい!
インスタントのお味噌汁を追加するだけでも◎
ヨーグルト
乳酸菌といえばこれ!朝ごはんにプラスしてみて
チーズ
乳酸菌とカルシウムが豊富。
キャンディタイプなど、さまざまな形があるのも魅力的。
納豆
ご飯のお供に!
良質なタンパク質も同時に摂れます!
【食生活を考える】食物繊維のことを知って、食事に取り入れる
食物繊維は
「ヒトの消化酵素で分解されない食物中の総体」。
水溶性食物繊維と不溶性食物繊維がある
水溶性食物繊維
腸内で分解されたら、善玉菌のエサになってくれる。
不溶性食物繊維
腸内のお掃除に一役買ってくれる。
どう食べる?発酵食品+食物繊維
【カラダを動かす】 毎日取り入れられる、かんたんすっきりエクササイズに挑戦する
exercise01 お腹ひねり体操
椅子に浅く座って足を組み、上の足の方向にカラダをねじった状態で深呼吸を大きく10回。
深呼吸をするときは、息を吸うときにお腹をふくらませ、息を吐くときにお腹をへこませるイメージで。肩がすくんだり、無駄な力が入ったりしないように注意しましょう。反対側も同じように行います。
exercise02 お腹伸ばし体操
椅子に浅く座ったまま、背筋を伸ばします。片手をまっすぐ上げ、脇腹の筋肉を伸ばすようにカラダを横に倒したまま、深呼吸を10回する。
このとき、カラダは真横に倒すように気をつけて。腹筋に力を入れるのがコツ。反対側も、同じようにカラダを倒します。必ず、お腹を意識しながら行ってくださいね。
exercise03 赤ちゃんのポーズ
仰向けに寝て両ひざを立て、両手でひざを抱える。手が届かない場合は、ひざに手をかけるだけでもOK。背中をできるだけ動かさないように、重心を左右にゆらゆらと移動させる。
キツくない程度、楽な気持ちで行うのが◎。呼吸は自然呼吸で大丈夫。寝る前に取り入れてみて。