紅茶がつくる、誰かと一緒のあたたかい時間
2026.01.30
#essey
essey


2026.01.30
#essey

2025.12.19
#essey

2025.11.21
#essey

2025.10.24
#essey
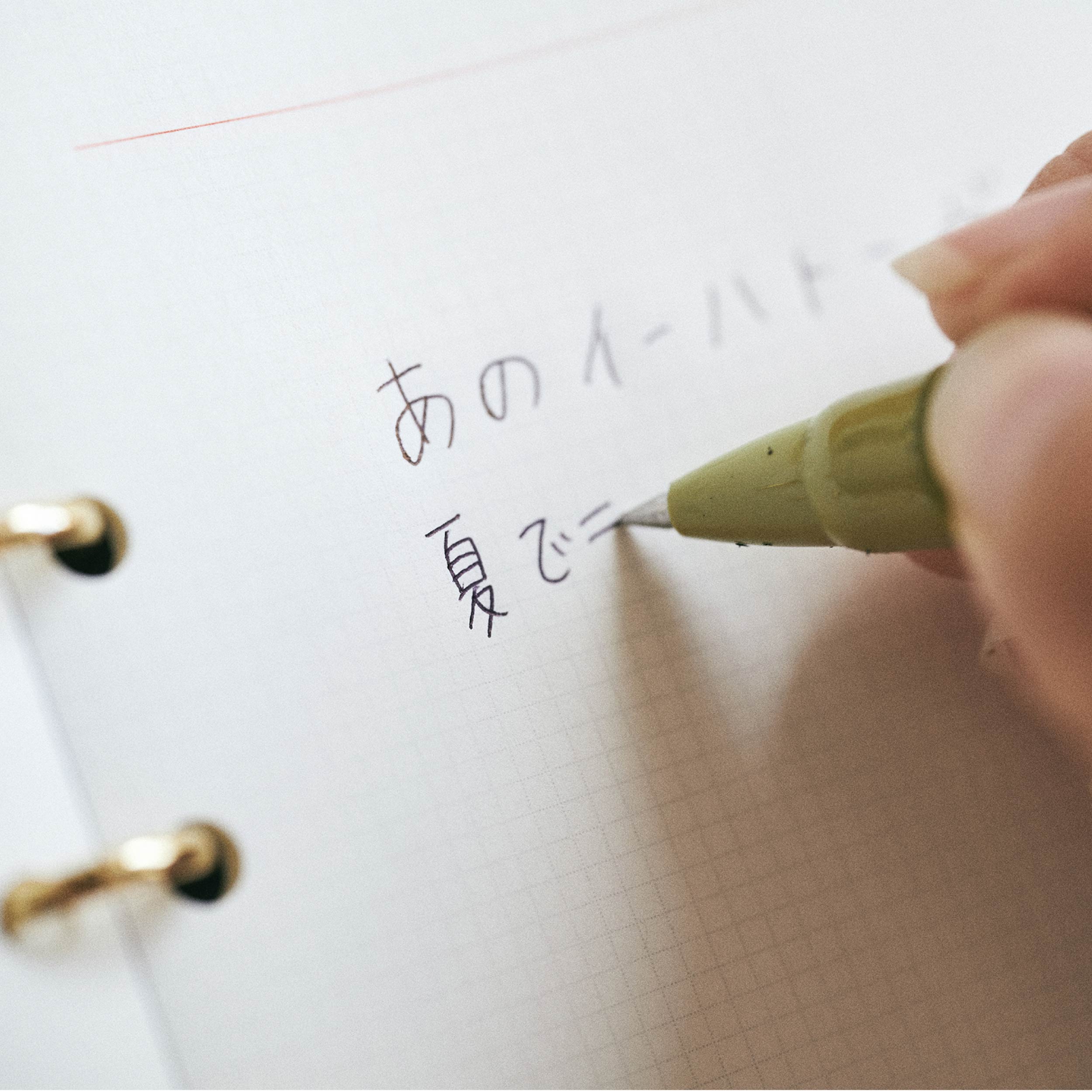
2025.09.26
#essey

2025.08.12
#essey

2025.07.22
#essey

2025.07.01
#essey

2025.06.30
#essey
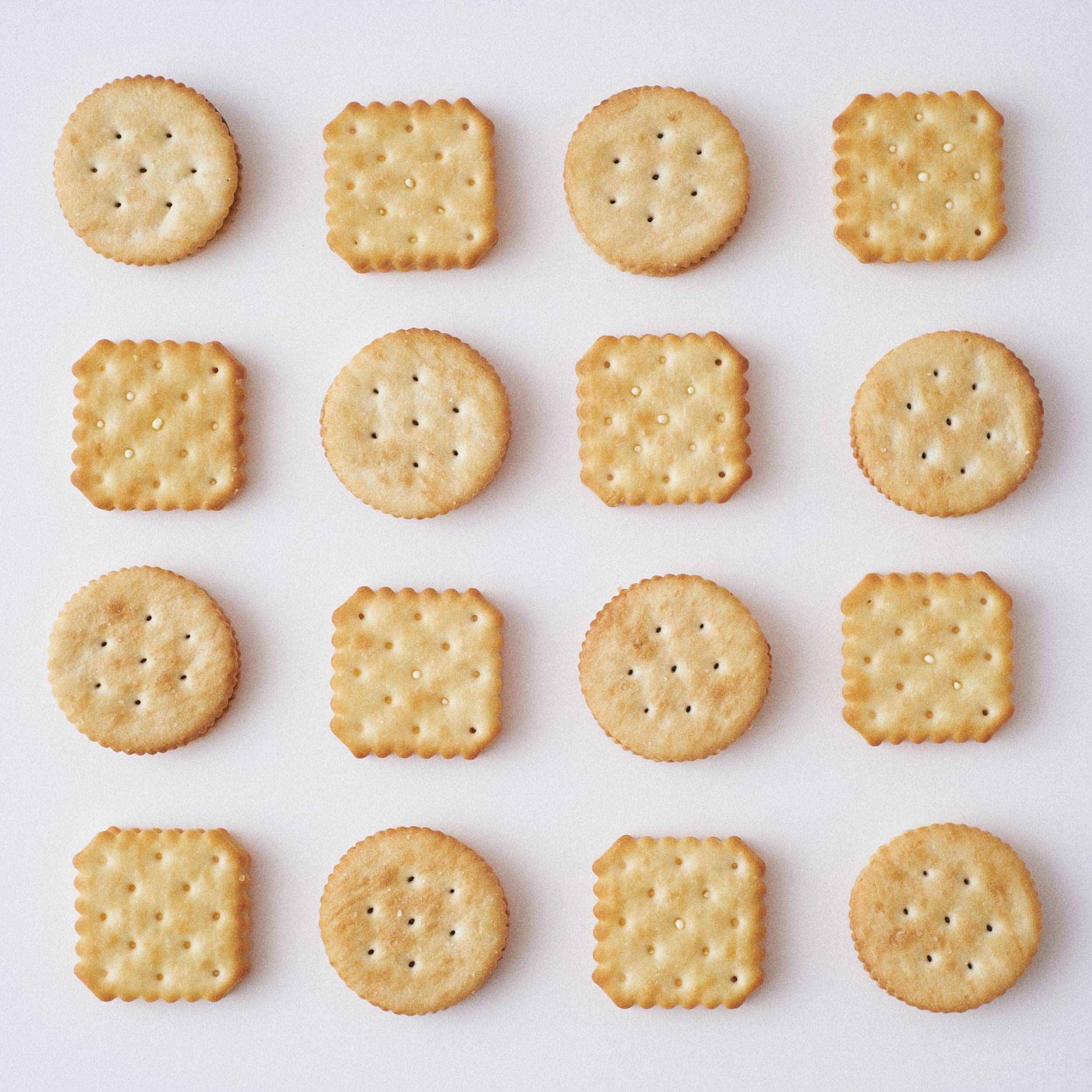
2025.06.11
#essey