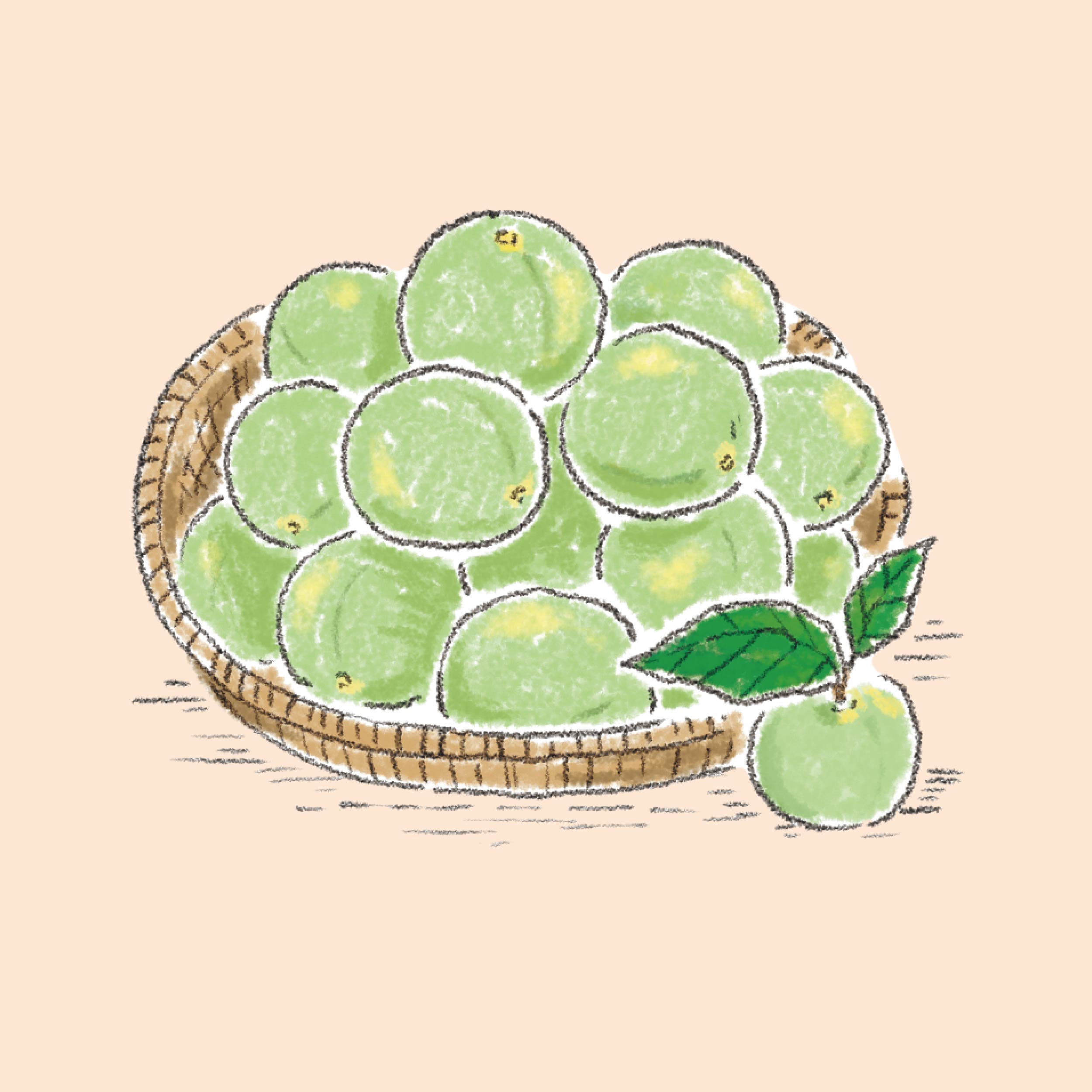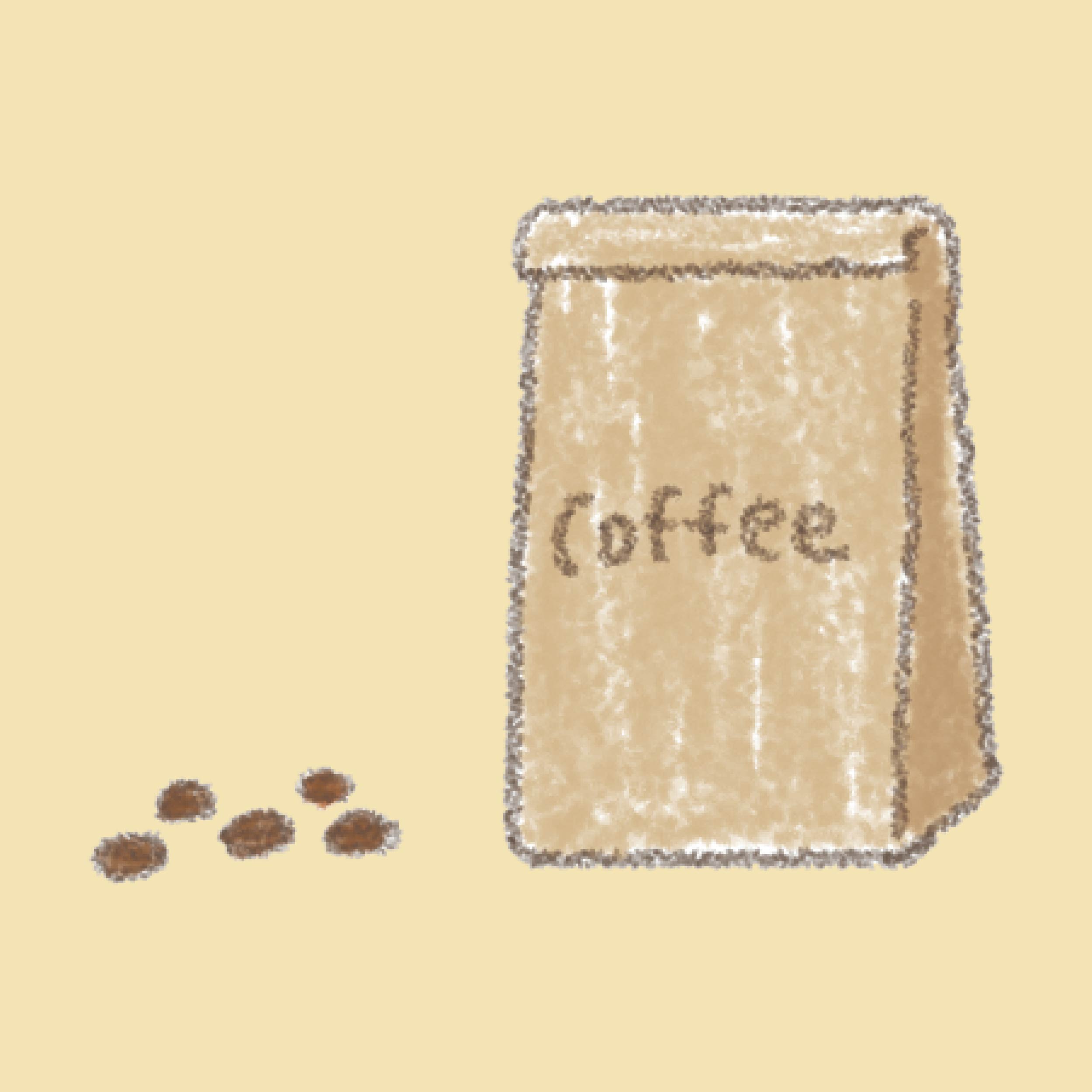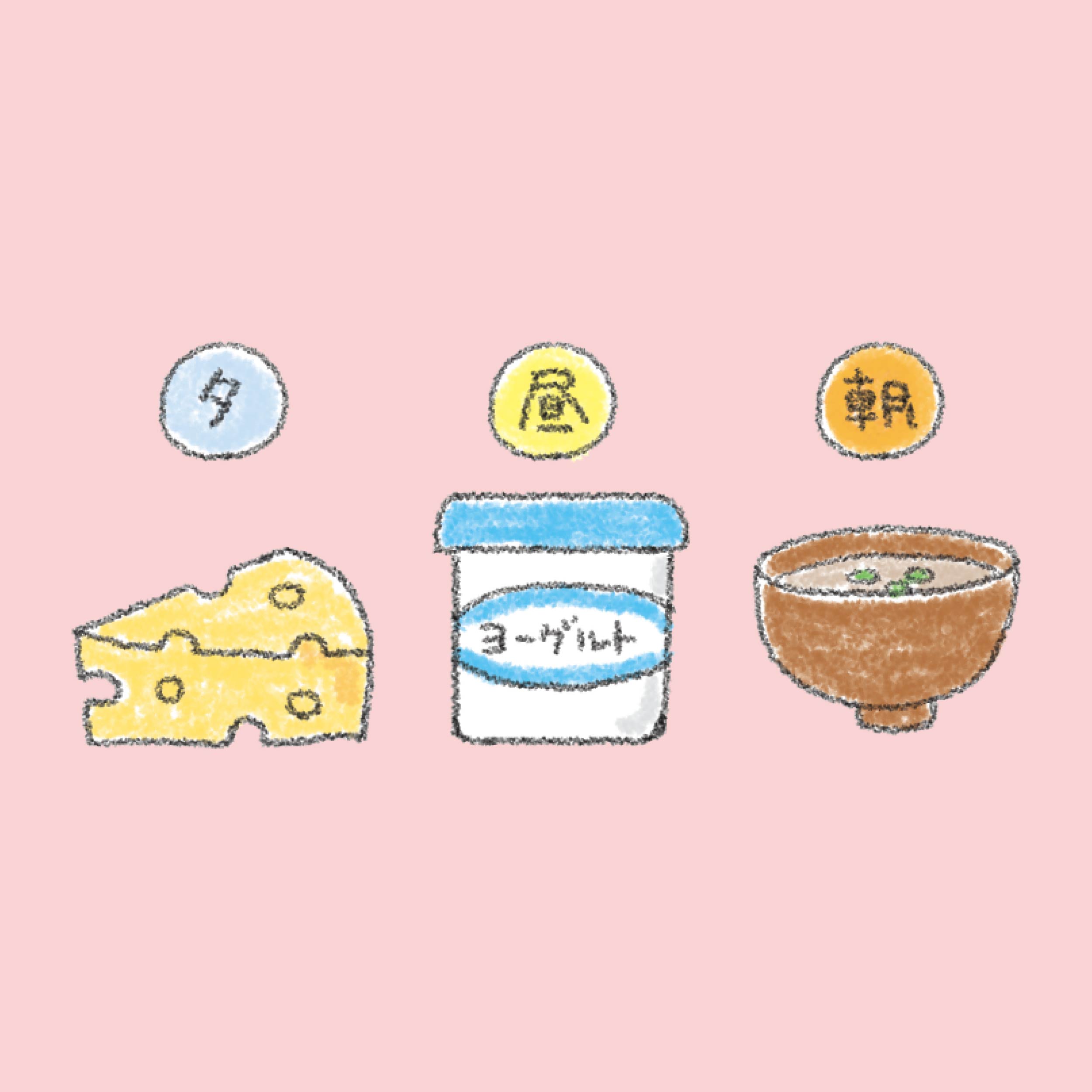グリーンのある暮らし
深呼吸したくなる。グリーンのある暮らしのはじめ方。
目に入るだけでなんだかホッとできて、空気清浄効果もある。そんな天然のヒーリング効果があるグリーン。お花よりも比較的お世話に手がかからないものが多く、気になるなと思っている方が多いのではないでしょうか。床置き、卓上鑑賞、吊るしてみる......飾り方も自由なグリーンのある暮らしをはじめましょう。
ところで、エコ・プランツってなにか知ってる?
エコ・プランツという言葉を聞いたことはありますか?観葉植物の中でも、空気をキレイにしてくれる効果に優れた品種のことです。
エコ・プランツを室内に置くことで、カビやバクテリアといった細菌の発生を抑えてくれるだけでなく、植物から出される水分が湿度まで保ってくれるんです。置いておくだけで部屋の清浄効果もあるため、何を取り入れたら良いか分からないという方は、エコ・プランツの中から選んでみると良いかもしれませんね。
グリーンを飾るときのコツ
たまには向きを変えてあげる
植物は太陽に向かって伸びるため、向きを変えてまんべんなく日光に当ててあげることも大切。日当たりが悪い場所に置くと元気がなくなってしまうことも。
座ったとき、よく見える場所に
人は一息つきたいタイミングで椅子やソファに座ることが多いため、自然と目に入る位置や高さを考慮して配置すると、よりリラックス効果を得やすくなります。
枝の先に空間ができるように配置
室内にグリーンを飾るときは、空間に対して少し余裕のあるサイズの木を選びましょう。枝の先に空間があることで成長した先の姿を想像でき、さらに魅力が増しますよ。
置き場に困ったら、無機質な場所に
部屋のどこに置くか迷ったら、テレビやPCの周りなど無機質になりがちな場所に配置してみて。少しグリーンが見えるだけで、優しい雰囲気が出ますよ。
グリーンインテリアレポート
hugkumi+スタッフ 西村
社会人になってから観葉植物を少しずつ集めはじめ、今では部屋いっぱい植物のたちと暮らす西村。次は壁掛けできるコウモリランを狙っているそう。
部屋に植物を置き始めたのはどうして?
最初は、母の影響でした。もともと母の趣味がガーデニングで、実家にいた頃から植物には慣れ親しんでいたんです。そんな母が、一人暮らしの家に置くドラセナを選んでくれたところからわたしの植物と暮らす生活が始まって、だんだん自分でも買い集めるようになりました。
一番のお気に入りは、初めて自分で購入した観葉植物のエバーフレッシュ。それ以降、ウンベラータにモンステラなどの大きめのものから、アイビーやローズマリーなど小さめの鉢植えまでどんどん増えています。
部屋のお気に入りスペースはさまざまな植木が置かれた窓枠。
アイビー、ローズマリーなど小さめの植木をまとめて置いてある出窓のスペース。家に帰ってきたとき、一番に目に入る場所だからこそ癒しのスペースにしたかったそう。半日向でもよく育つ初心者向けの植物やサボテン・多肉植物なら失敗も少なく、始めやすいですよ。
水やりは朝のルーティンに。季節によって頻度は変わります。
朝起きたらまず植木をベランダに出し、水をあげるところから1日がスタート。水が切れるまでの間に自分の身支度を済ませ、出かける前に家の中に入れて出発するそう。夏場は2日に1回程の水やり頻度。伸びた葉は切りそろえ、花瓶に挿して楽しむこともあるんだとか。
初心者でもお世話かんたん!小さめ鉢植えリスト
No.1 アイビー
〇 日当たり ・・・・ 日向
〇 水やり ・・・・・ 普通
〇 気温 ・・・・・・ 0~3度まで
できるだけ日向で育てたいところですが、明るめの日陰でも育ちます。たまに日光に当ててあげると◎。風通しが悪いと虫がつくので注意が必要です。比較的寒さにも強いので、暖地であれば外で越冬も可能ですよ。
No.2 リプサリス
〇 日当たり ・・・・ 半日向
〇 水やり ・・・・・ 乾燥ぎみ
〇 気温 ・・・・・・ 5度まで
直射日光を避けたレースカーテン越しの明るい日向が大好きです。乾燥が好きな植物なので、土が乾いて葉にシワが寄りはじめたらたっぷり水やりを。葉や茎からも吸水できるので霧吹きで葉水してあげるのも◎。
No.3 ポトス
〇 日当たり ・・・・ 半日向
〇 水やり ・・・・・ 乾燥ぎみ
〇 気温 ・・・・・・ 5度まで
強い日差しが苦手なので、室内の明るい窓際が管理にちょうど良いです。寒さに弱いため、冬は室内に入れてあげて。最低気温が20度を下回ると水を吸い上げなくなるため水やりの頻度は減らしましょう。
No.4 アジアンタム
〇 日当たり ・・・・ 半日向
〇 水やり ・・・・・ 好む
〇 気温 ・・・・・・ 8度まで
夏場は2回ほど水をやり、葉水も頻繁に。直射日光だと葉がチリチリになってしまうので、日陰に置きましょう。
部屋のシンボルツリーに!大きめ鉢植えリスト
No.1 ウンベラータ
〇 日当たり ・・・・ 日向
〇 水やり ・・・・・ 普通
〇 気温 ・・・・・・ 15度まで
寒さに弱いため、9月~10月には室内に移動を。夏の暑さには強いですが、風通しには注意しましょう。水やりは土が乾いたらたっぷりあげて。葉が黄色くなっている場合は日照不足なので、明るいところで日光浴を。
No.2 エバーフレッシュ
〇 日当たり ・・・・ 日向
〇 水やり ・・・・・ 好む
〇 気温 ・・・・・・ 10度まで
日当たりの良い明るい場所を好みます。日中は葉が開き、夜は閉じますが、水が不足すると昼も葉が閉じたままになることも。風通しが悪いと虫が付きやすいため、こまめな葉水で予防しましょう。
No.3 ベンジャミン
〇 日当たり ・・・・ 日向
〇 水やり ・・・・・ 普通
〇 気温 ・・・・・・ 10度まで
新芽の出る春から夏は水切れに注意。ときどき葉水してあげましょう。冬は土が乾いてから2~3日経ってから水やりを。環境が急に変わると葉が落ちてしまいます。様子を見ながら徐々に移動して。
さいごに
今回は部屋に彩りを与えてくれるグリーンをご紹介しました。彩りだけでなく清浄効果もあるエコ・プランツも素敵ですよね。
少し気になるかも……という方は、自分が始めやすい大きさや種類でぜひチャレンジしてみてください♪