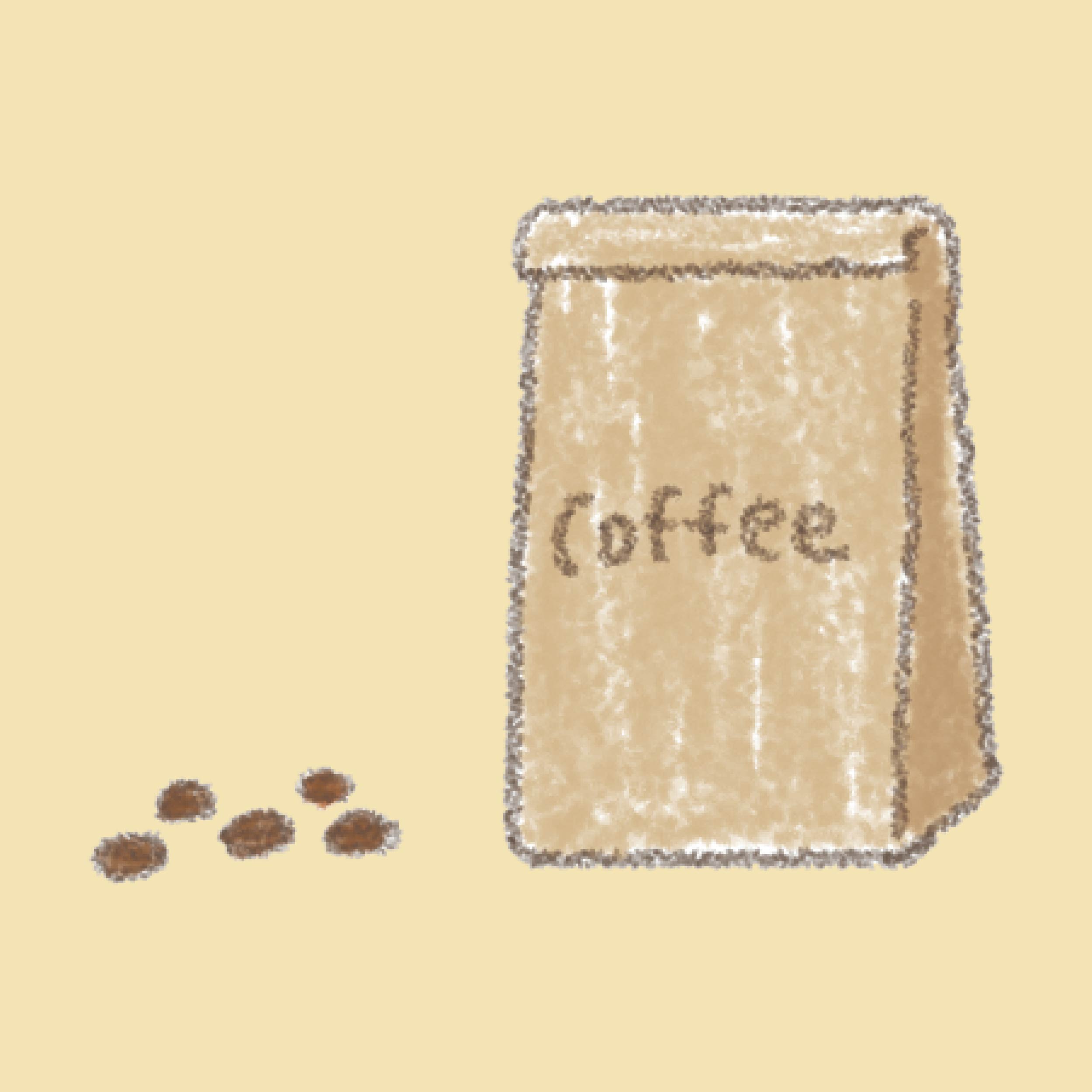cocone Winter Collection 2025 特別イベントを開催いたしました!
いち早く今年のWinter Collectionを体験できるイベント 毎年、冬が近づく頃に数量限定で販売しているcocone Winter Collection。 「長くご愛用のお客様にもっと喜んでいただきたい」「coconeをずっと愛用してくださるお客様に、特別な体験を届けたい」という想いから生まれた企画です。 実は、毎年1年ほどの時間をかけて、企画者がどんな思いを届けようか、どんな香りのシャンプーが喜ばれるだろうか……と何度も試行錯誤を重ねて準備を進めている、coconeブランドのなかでも特別な企画なんです。 そんな2025年のWinter Collectionをmご愛用いただいているみなさまにいち早く、かつ直接お届けできないか。そんな想いで、今回始めてとなるイベント開催に踏み切りました。 2025年のWinter Collectionは、スパークルリリーの香り ご参加いただいたお客さまには、Winter Colectionの発売に先駆け、スパークルリリーの香りをひと足先にご体験いただきました。 シャンプー、ヘアマスクの香りの体験はもちろん、ヘアオイルを髪や腕につけていただき実際の香りをつけていただき、ネットショップではなかなか実現できない「ご購入前に実際に手に取っていただく」ことが可能に! ご参加いただいたお客さまからも、「購入前に実際の香りを感じられるのが嬉しい!」とお声をいただくことができ、わたしたちも一安心。 さらにお楽しみいただける装飾やイベントをご用意! 今回のイベントの主役は、「歴代のWinter Collectionの香りを使ったオリジナルバスソルト作り」。 これまでのWinter Collectionの中から4種類の香りをご用意し、お好きな香りを使ってオリジナルのバスソルトを作っていただきました。 実際に歴代のウィンターコレクションを使ったことがあるお客さまも多く、中には全種類使ったことがあります!というお客さまも。 どの香りが好みかや、今までどのシャンプーを使ったことがあるかなど、スタッフとはもちろん、ご参加いただいたお客さま同士でも話に華が咲きました◎。 また今回は、バスソルト作りの他にも歴代のWinter Collectionの香りと企画者の想いの展示に加え、お客さまから募集した「クリスマスの想い出」エピソードも展示。 うっとりするような素敵エピソードから、くすっと笑えるものまでたくさんのエピソードをいただけました! みなさまからのお声を直接伺える機会に スタッフとお客さまが個別でお話しする時間もたくさんあった今回のイベント。 新たなブランドの商品を実際に使っていただいたり、hugkumi+の開発秘話について知っていただいたり……。商品について感じていたことや、coconeの好きなところなどお客さまから直接お聞きできるとても貴重な時間を過ごせました^^ ご参加いただいたお客さまからのお声 ♥ 人数の少ないイベントだったからこそ、スタッフさんとの直接の会話がゆっくりでき、商品への思いを直接伺うことができて、これから商品を使うときに大切に使っていこうと感じました。 「いい商品をお客様に届けたい」というハグクミプラスさんの思いがとても伝わってきて、いい企業さんだと感じました! ♥ 私が昨年のメルティダージリンの香りがすごく気に入っていたことや他の商品にも興味を持ったこと等を覚えておられて、本当に会員に寄り添っていて素敵な会社だなぁと感じました。 なんとなく参加したイベントですが、hugkumi+のファンになりました。 また機会があれば、イベントに参加したいです。 今後もシャンプーを始め、他の商品も試してみようと思っているので、長い付き合いになりそうです! こんなに丁寧で素敵な会社はなかなかないと思います。 ♥ ずっと良い香りに包まれて、楽しい時間を過ごせたことが生活している中ではなかなかないので贅沢な時間が過ごせました。 さいごに、 企画者井上より 普段はなかなか直接会うことのできないお客さまとお会いできて、本当に楽しい時間でした! 「悩んでいた髪が落ち着いた」「髪悩みが解決した」などの嬉しい言葉を直接聞くことができて、もっといい商品を届けられるように頑張ろう、という気持ちがより一段と高まりました。 ウィンターコレクションの感想も直接聞けて嬉しかったです^^ お客さまの笑顔にパワーをいただきました!絶対にまたイベントを開催したいです!2025.11.28
#notice